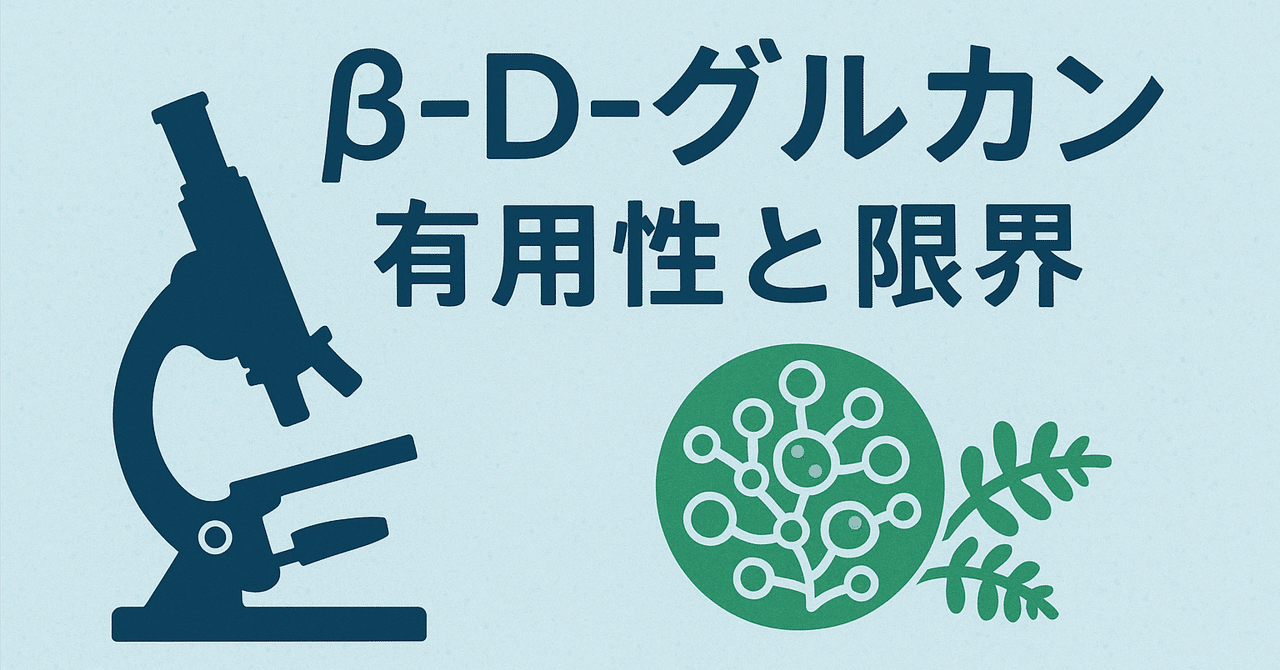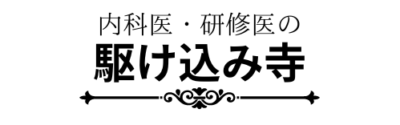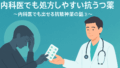はじめに
「β-Dグルカン高値につき真菌症の可能性について評価お願いします」
っていう文面よく目につきますが、これってそもそも
参考文献
感染症クリスタルエビデンス(診断編)
(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784765319775)
β-Dグルカン
β-Dグルカンは真菌の細胞壁を構成する多糖体であり、多くの侵襲性真菌感染症で上昇することが多いとされているものの
・そもそも菌種特異的ではない
・クリプトコッカス、ムーコル症では基本上昇しない
・偽陽性となる原因が多数存在
β-Dグルカンの偽陽性の原因
セルロース素材の透析膜を用いた血液透析
(現代では少ない)
血液製剤(アルブミン、グロブリン、凝固因子)
ペニシリン系抗生剤
ガーゼ(手術で大量使用した場合)
etc,,,
ということで陽性になったところでそもそも真菌感染かも不明で、菌種の特定も不可能なので治療方針の決定打となり得ない、という印象の検査です。
なので結論から言うと、目の前の発熱患者に対して、β-Dグルカンが陽性であったところでその単独の結果で抗真菌薬使用を決定することはないし、どの抗真菌薬を使用すべきかも示唆しない検査項目です。よくわからん熱発が出ている患者で測定しても余計なノイズが増えるだけなので基本おすすめしません。
では、どんな時に測定の意義があるのか。
β-Dグルカンの測定目的
⭐️そもそもの鑑別疾患となる
真菌感染症の検査前確率の
見積もりをした上で①侵襲性真菌感染症の除外
②侵襲性カンジダ感染症の疑いが強い
患者に対する抗真菌薬の開始③ニューモシスチス肺炎の
診断補助
きちんと内科の勉強をしてる人は検査前確率がいかに大事かがわかると思います。そもそも検査前確率の低い患者に対して感度、特異度がいい検査をしたところで偽陽性、偽陰性の確率が高くなります。
ということで「そもそも検査結果が信頼できない」という状態に陥ります。ならその検査やる意味ありましたか?っていう話(詳しく勉強したい人はぜひググって)。
なのでβdグルカンを図る際は何の真菌症に対する精査なのかを自分で言えなければ、測定する意義に乏しいです。