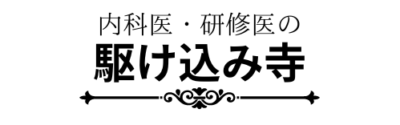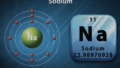はじめに
血液ガスの分析ができるようになると、だんだんこういう感覚になります。
「結局分析したところで鑑別そんなに変わらなくね」
「トリアージには役立つけど、、、、」
そうなんです、緊急疾患の早期発見には役立つし電解質もすぐわかる優れものなんですけど、結局分析をしたところで実際のアセスメントに関わる状況ってあんまりないんですよね。
1番の問題が
アシドーシスはわかるけど
結局何をどうすればいいのよ
という痒いところに手が届かないのが勿体無い。
お待たせしました、ここで応用編のStewart法(正式には簡易Stewart法)
これを知っておくと血ガス分析に一気に深みが出ます。ぜひマスターしましょう。
参考文献
簡易Stewart法
平たく言うとアシドーシス、アルカローシスに関わる分子を数字で定量化したのがStewart法です。正式なStewart法は実臨床ではとても使える方法ではないので割愛します。
血液ガス分析〜簡易Stewart法〜
各項目を計算する
(正負も評価のうち!)①;Na-Cl-36
②;1-Lac
③;2.5✖️(4.2-Alb)
④;sBEー①ー②ー③
※sBE=standrad Base Excess〜実際の分析〜
正の値はアルカローシス
負の値はアシドーシスに関連値の絶対値が大きいほど影響力が大きい
①;Na-Cl-36
高Cl性アシドーシスって聞いたことありますか?生理食塩水をばかばか補液するとアシドーシスになるよっていう一時期問題になった病態のことですね。
Clが増えると同じ陰イオンのHCO3が相対的に減る(何いっているかわからないですって?病態生理が気になる探究心多めなあなたは、ぜひ参考文献を読んでしっかり勉強しちゃってください)。
塩基性物質であるHCO3が減るからアシドーシスに傾くってわけですね。同様の理屈でNaも考えてください。ただし陽イオンのNaと陰イオンのClは理屈が逆なので、Naが減るとアシドーシスになります。
なのでNaとClの差をとるとちょうどいい指標になって
Na-Clが低い→Naが減ったかClが増えている→いずれにせよアシドーシス
という形で使えるわけです。
- Na-Cl-36>0 Na↑、Cl↓による代謝性アルカローシス
- Na-Cl-36<0 Na↓、Cl↑による代謝性アシドーシス
※なので採血でNaとClが解離している場合(差が40以上ある場合)はなんらかの酸塩基平衡の異常が
②;1-Lac
これは簡単、乳酸が大きいほど乳酸アシドーシスになるってわけですね。
③;2.5✖️(4.2-Alb)
低アルブミン血症はアルカローシスになります(アルブミンが塩基性物質なので)。それを基準値の4.2と差をとって係数の2.5をかけるだけです。
④sBEー①ー②ー③
まずBE(Base Excess)とは、体内の塩基性物質の総量です。なのでこれが正の値なら代謝性アルカローシス、負の値なら代謝性アシドーシスとなるわけです。めちゃめちゃ大雑把な解説なので、詳細は参考文献を(略)。sがなんで前についてるの?って話も参ry
もちろん体内の総量ですから、乳酸やCl、HCO3なども含めた値になります。なのでせっかく計算したNa、Cl、乳酸(lac)、Albの値を取り除くと、残るは採血で計算されない(乳酸以外の)不揮発酸が出てくるというわけです。
BEー(①+②+③)=乳酸以外の不揮発酸
この中身はP(リン)やケトンなどです。なので④が負の値ならリンやケトンの蓄積で代謝性アシドーシスになっていると判断しています。
個人的に、この値が高めなアシドーシスがいたら真っ先にケトアシドーシスを疑います。
症例検討
症例検討(自験例です)
ICU入院中の糖尿病患者
day 3
敗血症ショックで挿管中バイタル変化はないがアシドーシスが出現している
pH 7.30 , PaCO2 32, HCO3 15, Na 140, Cl 113.
Lac 3.0, sBE -17 , Alb 2.2, Glu 180.1, pHは?
→軽度のアシデミア2, 一次性変化は?
→アシデミアなのでアシドーシス
HCO3が低いので
代謝性アシドーシスがメイン3, 二次性変化(代償性変化)は?
→予測pCO2=28<実測pCO2で
呼吸性アシドーシスの合併あり4, AG(アニオンギャップ)を計算する
AG=12でAG開大性アシドーシスなし
5, 補正HCO3-を計算する
AG開大性アシドーシスないので計算不要
6, 臨床状況と照らし合わせる
→AG非開大性代謝性アシドーシス+呼吸性アシドーシス→代謝性アシドーシスは敗血症のせいだな
なんだ、換気量が足りないから
アシドーシスになってるのか
じゃぁ換気量を増やして、、、、、
え、みなさん何も思いませんでした上の文章?
だとしたら少し洞察力が足りません。
まず上の分析で気づかなければいけないのは、、、、、、、
いや、乳酸あがってるやん
AG開大性の乳酸アシドーシスじゃん
そうなんです、計算だとAGが開大してないのに乳酸が思いっきり上昇しているってのは実臨床(特にICU患者)だとあるあるです。AGの計算が乳酸アシドーシスの検出において、感度が悪いっていうのはいろんな論文で指摘されています。
あと私がオーベンなら、上の分析をしてきた研修医がいたらこう言います。
「じゃぁ代謝性アシドーシスの原因ってなんなのよ、敗血症性ショックは普通AG開大性アシドーシスでしょ。治療してるのにアシドーシスがよくなってないって気持ち悪くない?」
はい、いやなオーベンですね。ですがこう言う風に自分の分析と実臨床の経過が一致しているのか、常に確認する癖をつけるのは患者を急変させないために非常に大事でございます。
こう言う時こそStewart法の出番です。
症例検討
ICU入院中の糖尿病患者
day 3
敗血症ショックで挿管中バイタル変化はないがアシドーシスが出現している
血液ガスをした。pH 7.30 , PaCO2 32, HCO3 15, Na 140, Cl 113.
Lac 3.0, sBE -17 , Alb 2.2, Glu 180.①;Na-Cl-36
=ー9<0②;1-Lac
=ー2<0③;2.5✖️(4.2-Alb)
=5>0④;sBEー①ー②ー③
=−11<0
※sBE=standrad Base Excess
負の値が多く、絶対値の順番に並べると
④>①>②となります。低アルブミンのおかげで多少軽減されていますが、アシドーシスまみれの病態であることがわかるでしょう。
数値的に影響順としては
(乳酸以外の不揮発酸)>高Cl>乳酸上昇
となります。Clを不要に補充しない(メインや溶媒をブドウ糖にする)ことも重要そうですが、原因不明の不揮発酸が1番の原因っぽい。
糖尿病患者で重症疾患が多いICUで真っ先に疑うべきなのは、、、、、、。そう、糖尿病性ケトアシドーシスですね。栄養内容やSGLT2阻害剤の内服も確認したいところではありますが、アシドーシスの迅速な補正が優先でしょう。尿ケトンの確認やケトン体の迅速測定ができる病院であれば真っ先に測定しましょう。
んで上記状況、僕だったらインスリンの静注開始してしまいます。低血糖さえ気をつければ副作用もほとんどないし、アシドーシスがよくなればケトアシドーシスと(ほぼ)臨床診断できますしね。
おわりに
いかがでしたでしょうか。このStewart法は代謝の分析のみで呼吸の分析はできないってところが弱みですが、病態分析に非常に役立つ手法です。
ぜひ自分で手を動かして見てください。