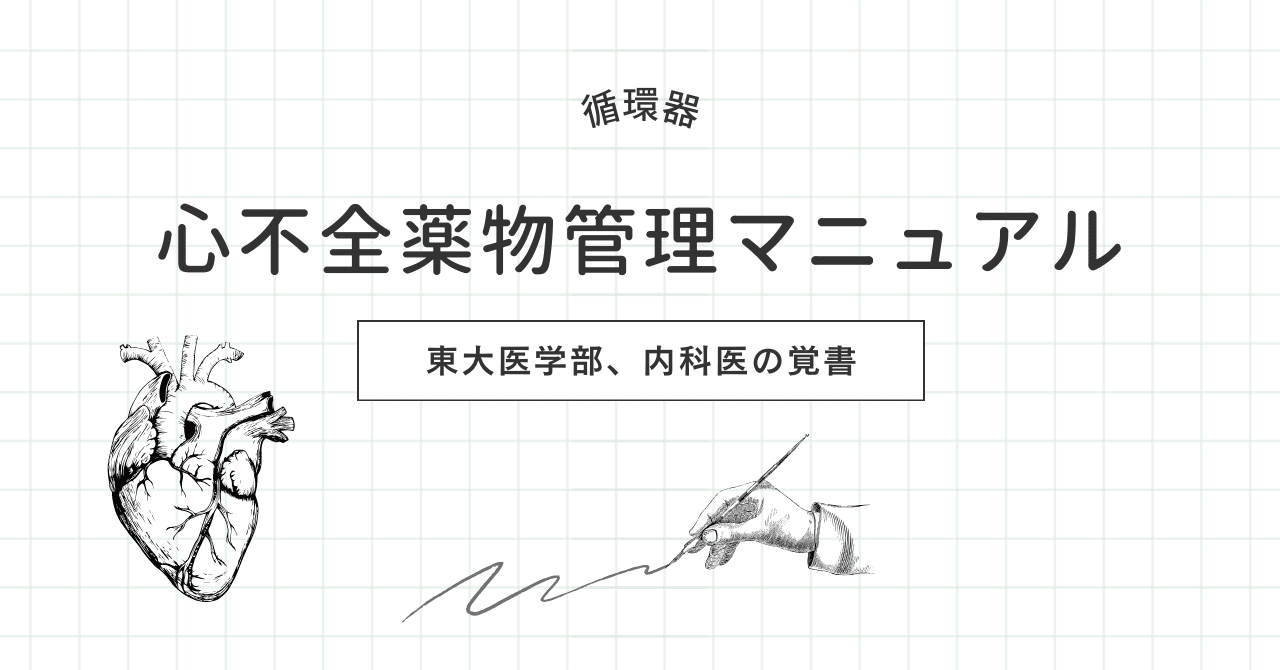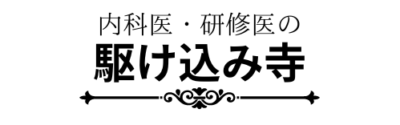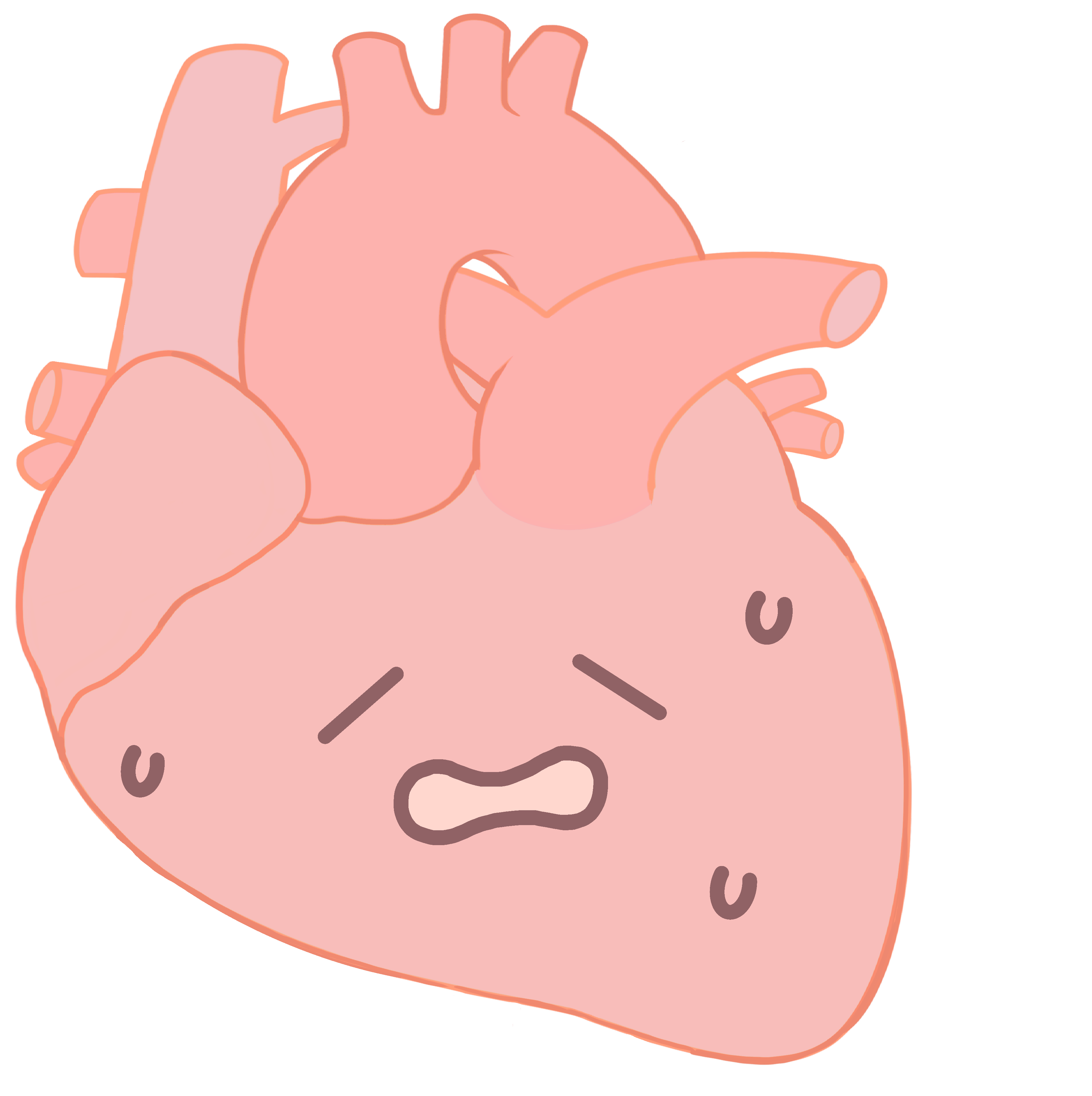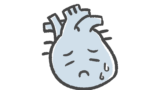はじめに
HFrEF(EFが40%以下の慢性心不全)において、fantastic 4の4剤は導入必須。各薬剤の特徴とやり方、どういう時に減量、増量、中止すべきかも簡単に解説。
また、救急外来で来た心不全はfantastic 4とか言っている場合ではなく、静注薬での対応が必須になってきます。以下の記事と合わせて読み込んでおきましょう。
心保護薬一覧
心保護薬
〜fantastic 4〜
- RA系阻害剤(ARNI含む)
- β遮断薬
- ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)
- SGLT2阻害薬(SGLT2i)
※ショック患者の場合全て即中止
ちなみに、ショックやLOS状態の患者では上記内服は全て中止してください。血圧を下げたり、利尿効果がある内服なのでLOSを悪化させます。
RA系阻害剤(ARNI含む)
言わずとしれたACE阻害薬(ACEi)、アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)、そして比較的新しいARNIの3種類で、ARNIはARBの強化版だと思っときましょう(正式にはARBのバルサルタンとネプリライシン阻害剤のサクビトリルの合剤)。
全て降圧効果がある内服で、ARNI>ARB>ACEiの順に降圧効果が強いです。
この中でHFrEFに一番エビデンスがあるのはARNIです。なのでHFrEFではARNIの導入を目指していく方針になります。
が、いきなりARNIの導入はせず、まずはACEi/ARBの導入を行った上でARNIにスイッチするという方法が一般的です。
ACEiを内服していた場合は36時間あけてからARNIの導入をするべきと添付文書に記載されており、この手間をとるのが面倒なので初手ARBを使用する場合が多いですね。
しかし収縮期血圧100未満や重症心不全だった場合、ARBでは血圧が下がりすぎる場合があるので初手はACEiを導入することも。そんな時に使うのは降圧降下弱めな薬物が安心ですよね。なので、ACEiの中ではエナラプリル(レニベース)が使用されることが多いです。
注意点として腎機能障害(AKI)、高カリウム血症があり、有害事象の際は減量、中止を検討しましょう。ACEiは咳嗽が副作用として出現する場合があります。
ただし、何も考えずいきなり中止するのも考えものです。いきなり血管拡張薬、降圧薬をやめることになるのですから、心臓にとっての後負荷があがるはず。最悪の場合中止のせいで肺水腫になります。
なのでAKIや高カリウム血症でもHFrEFで導入している場合は
- ARNIなら
バルサルタン40mgへのgrade down - ARBやACEiは半量への減量
を検討しましょう。ただ、カリウムが6以上とか、Creの値が2倍になっているなど重症感が強い場合は中止せざるを得ないでしょうね。臨床状況に合わせて判断してください。その場合代替薬の降圧薬としては、腎機能や電解質に関係ない血管拡張薬の硝酸薬がいいでしょう。
上記通り、副作用として腎機能障害や高カリウム血症があるのでCKDだと使用を敬遠する人がいるかもしれませんが、むしろCKDがある人ほど腎保護作用があるのでARB/ACEiを使用するべきです。そして腎機能は多少悪くなっても使用を続けて大丈夫(Cre比で30%までの上昇なら許容、むしろ使い続けた方が腎保護作用が期待できる)です。詳しくはガイドラインを見て下さい。
増量に関しては、収縮期血圧120前後を目指してのコントロールが良いですが、心エコーも頻回に行えるならE/A 、E/e” 、などの左房圧パラメータもみながら調整するとなおよし。
β遮断薬
使用薬はビソプロロール(メインテート)かカルベジロール(アーチスト)です。アーチストは心不全では分2で使用する必要があります。コンプライアンス的にはメインテートに軍配があがりますが陰性変時作用(HRを下げる作用)も強いので、HRが下がりすぎないように注意しましょう。
目標心拍数は安静時HR75未満がガイドラインだと推奨されています。そしてできるだけ最大量まで増量することが心不全の予後を改善させるので大事。
しかし、fantastic4の中で一番扱いに注意すべき薬剤で、陰性変力作用(心臓収縮力が下がる)もあるため血行動態の悪化、うっ血症状の出現や増悪のリスクがある薬剤です。なので
- うっ血症状が消失し、症状が安定している
- 血行動体が安定していること
(原則カテコラミン使用をしていない状況)
の2つが確認できなければ導入、増量すべきではありません。
上記理論から心不全の増悪で入院した場合は即時中止、、、、、ではなくて継続する必要があります(ややこしいですね笑)。
なぜならHFrEFでβ遮断薬を中止すると予後が悪くなるという研究が散見されており、心不全の急性増悪(主にうっ血所見の増悪)でもなるべく継続することが推奨されています。筆者は外来量の半分に減量して継続しています。
しかし、心不全でもcoldの所見(いわゆるLOS)がある場合は、基本カテコラミン使用する必要があり、β遮断薬はカテコラミンの効果を減弱させるので中止せざるを得ないでしょうね。補助循環を使用する場合もしかり。
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)
※2025/2 非ステロイド骨格を有するMRAのエビデンスについて追記
アルダクトンA(スピロノラクトン)やセララ、エサキセレノン(ミネブロ)があげられます。
セララの方がアルドステロン受容体への選択性が高いです。スピロノラクトンはアルドステロン受容体への選択性が低く、プロゲステロンなどの性ホルモン受容体も阻害するため、長期に服用すると女性化乳房や乳房痛、不正性器出血等の副作用が生じる場合があります。セララの方が性ホルモン関連の副作用は少ないですが、薬価は多少高い(25mg錠で14円vs22円)ので、どちらにするかは患者と相談です。
薬理作用からK保持性利尿薬なんて言われることも多く、副作用として脱水による急性腎障害や高カリウム血症があげられます。
fantastic4の中では比較的導入しやすい内服ですが、どうしても高カリウム傾向になってしまう場合はカリメートやロケルマなどのカリウムを下げる内服、および栄養指導を検討してなんとかMRAの内服を継続する方向で話を進めたいところ。
ただ、ここもcase by caseです。例えば90歳の女性で容易に脱水になり高カリウムや腎機能障害で入院を繰り返しているとなると、、、MRAのおかけでどれだけ90歳のQOLがあがるかは微妙なところですよね(むしろ高カリウムの不整脈の方が予後を規定しそう)。上記症例で心不全が代償期であり症状が安定していればMRAの中止(や他利尿剤での代用)を検討していいと思います。
どんな薬剤でもそうですが、「エビデンスがあるから導入する!!」のではなくて、
- その薬物はどういうメリットがあるか
- 内服継続のメリットと有害事象のデメリットは目の前の患者ではどちらが優先されるか
を把握することが大事です。
※2024ESCにて非ステロイド骨格のMRAはHFmrEF、もしくはHFpEFに対してエビデンスを有する可能性があることが発表されました。
ステロイド骨格を持つMRAのスピロノラクトン(商品名:アルダクトンA)、 エプレレノン(セララ)に対して、比較的新しいステロイド骨格を持たないMRAのエサキセレノン(ミネブロ)やケレンディア(フィネレノン)がエビデンスがあるとされています。ESCで取り上げられていたのはフィネレノンでした。
千葉大学の先生がまとめを書いていたので参考にしてください笑。確かにSGLT2阻害剤にadd onして相乗効果があるかどうかは気になるところですね。
https://www.m.chiba-u.ac.jp/dept/cardiology/files/7417/2585/5355/Journal_Club_20240909.pdf
SGLT2阻害薬
いわずとしれた心不全薬のスーパースター。糖分を尿から排出する血糖降下薬であり、利尿効果もある薬剤。HFpEFでもエビデンスがある唯一の薬剤で、心不全患者で導入しないことはもはや許されない時代になってきました。
急性心不全でも利尿効果でうっ血の解消に役立つというエビデンスがいくつか出ており、血行動体にも大きく影響はしないので急性期でも導入しやすい内服です。
副作用として注意すべきなのは尿路・性器感染、低血糖と正常血糖ケトアシドーシス(uDKA)であり、食事摂取が不良(いわゆるsick day)であれば内服は中止すべきでしょう。
「でもとりあえず全例導入すればいいんでしょ?」って議論になりがちですが、、、、、実際はそうもいきません。
フレイルや低栄養患者では判断を迷うところですが、心不全患者に対する治療効果はフレイルの有無に関わらず同等と検証した論文もあり(出典忘れましたすみません、、、)、心不全が改善すれば低栄養やフレイルが改善する患者もいるので、「低栄養やフレイルだからSGLT2阻害薬を導入しません!!」って主張はやめた方がいい。
また、心不全入院患者だと尿カテが入っている人も多く、『SGLT2阻害薬が尿路感染を増やす』という明らかなエビデンスはあまりないものの(性器感染は多少増やすみたいですけど)尿カテ入っている人にほいほい使うのは、、、少なくとも私はいやですね。
筆者の基準として自分でトイレに行けるような状態になったら導入するようにしています(尿カテが抜けても、おむつつけている患者ではすぐ導入しようとは思えません、、、、)。
また、eGFRが15以下で検証した治験はないはず。なので極端な腎機能低下例では導入するメリットがあるか検討すべきです。
RA系阻害薬と同様、腎保護作用があるためCKDがあれば尚更追加したい内服です。しかし導入後に腎機能が一時的に悪化する(導入して2週間~2ヶ月程度)ことがあり、このinitial dropと呼ばれる現象は外来医として知っておく必要があります。
initial drop後はプラセボ群(つまりSGLT2iなしの群)より腎機能の増悪スピードが緩やかになるので、結果長期予後で見ると腎保護作用がある、と判断されたわけです。
なので導入して2週間~2ヶ月程度での無症状AKIは経過観察で良いのですが、薬剤の副作用とみなして一気に中止することがないようにしたいですね。
ただしeGFR30以下の場合、このinitial dropが来ると一時的に透析になる可能性があるため、その説明は患者にしておくべきしょう。腎機能が悪めの人であれば普段より頻回のフォローが推奨されます。
使用薬はエンパグリフロジン(ジャディアンス)やダパグリフロジン(フォシーガ)です。この2剤の比較論文(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24282)ではエンパグリフロジンの方が入院イベントを減らす可能性が示唆されていますが、容量に関する記載がないので「心不全にはジャディアンス!」と一辺倒になるのもどうなんでしょうね。
ジャディアンスは10mg、25mg錠、フォシーガは5mg、10mg錠があり、基本心不全に対する使用は10mgのはずですが、容量依存で利尿効果が高くなる可能性も否定できないので上記論文ではそこも検討して欲しかったですね(上記の比較論文も両者10mgでの比較ならジャディアンスの有益性が示唆されるはずですが、、、、)。
ジャディアンスの方はDPP4阻害薬との合剤がある(トラディアンスといいます)ので、内服状況によっては錠数を減らせるかも。まぁ心不全に対する投薬ならどちらでも大きい差はない、というのが現状でしょうか。今後の研究が待たれますね。
薬剤の導入量、増量、中止法について
以下1日A錠をB回に分けて内服→ATBxと表記します(6錠分3なら6T3x)。ちなみに心原性ショック後や血圧が低め(sBP90程度)など余裕がない症例の場合、以下の量の半量から私は導入しています。
基本的には1剤1剤を大容量入れることよりも4剤をなるべく早く揃える方がよいとされます。
増量は基本外来で行うものと考えておけばいいでしょう。導入も外来より入院で見た方が安全ですしね。
RA系阻害薬
ARB→ARNIへのスイッチが基本戦略(※最優先)
- バルサルタン40mg
1T1x内服開始- エンレスト50mg
2T2xにスイッチ(100mgを朝夕に分割)血圧が100以下や低心機能で
慎重に導入したい場合は上記の代わりに
☑️エナラプリル(レニベース)2.5mg
1T1xで開始※注意点
急性腎障害、高カリウム血症では
軽度なら半量への減量を検討
重症なら中止
β遮断薬
✅基本最大量までの増量を目指す
(血圧や本人の症状を見ながら)
✅増量後最低数日は同容量で
経過を見る
(※うっ血症状が増悪しないかcheck)
- メインテート0.625mg
1T1xで開始 max 5mgまで- アーチスト 1.25mg
2T2xで開始 max 20mgまで※導入後、増量後の注意点
体うっ血、肺うっ血が
増悪することがある※心不全の急性増悪で入院した場合
- coldの所見があれば中止
改善後、早めに再開- wetの所見のみなら
半分にして継続- 徐脈、気管支攣縮などの
有害事象の際も中止が推奨
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)
- スピロノラクトン 25mg
1T1xで開始- セララ 25mg
1T1xで開始※注意点
急性腎障害、高カリウム血症では
軽度なら半量への減量を検討
重症なら中止
※本当はミネブロ、ケレンディアも書きたいところなんですが、こいつらまだ心不全の適応が通ってないんですよね、、、、、。ミネブロは高血圧を有していたら投薬可能なのですが、、、、、。今後の動向に乞うご期待(2025/2 追記)。
SGLT2阻害薬
- フォシーガ 10mg
1T1xから開始- ジャディアンス 10mg
1T1xから開始※注意点
食事摂取不良、LOS状態であれば中止
実際の症例でどう導入していくか
さて、実際HFrEFの症例は非代償性心不全(いわゆる急性心不全)の状態で来て、エコーでEFが低下していることが発覚する、というのが圧倒的に多いです。
なのでこの記事では基本うっ血症状がある心不全症例にどう導入していくかを解説していきます。
なお、以下の方法論は筆者の自論なので、順番が違っても大丈夫です。私も患者背景によってminor changeしますし。
HFrEFに対するfantastic 4の導入の順番
(うっ血症状+の場合)
- MRA
- RA系阻害薬or SGLT2阻害薬
- 上記のもう一方
- うっ血取れたらβ遮断薬
さて、なぜ初手MRAとするかというと、消去法です笑。
まずβ遮断薬の導入が最後になることは共通認識で良いと思われます。できるだけ早く導入することが大事ですが、うっ血が悪化するようでは目も当てられません。
なのでまずうっ血解除を最優先、初期段階は利尿剤中心に攻めるべきです。利尿剤としてはSGLT2iかMRAということになります。
SGLT2iは急性期でもエビデンスが出てきており、確かにいい薬剤です。が、初日は尿カテ挿入して尿路感染リスクがあったり、意外と経過が悪く食事が食べられなくなったり(LOSになってしまったり)など、初日や2日目だと今後経過がどうなるか不安だな、、、って症例も多数あります。そんな患者でSGLT2iを内服させてDKAになったりしては目も当てられない、、、私は初手ではSGLT2iを入れないようにしています(もちろん、他の利尿剤でしっかり利尿をかける前提ですけど)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この辺は議論が分かれるところで、「そもそも稀な合併症のDKAを気にして、SGLT2iの導入を遅らせるのは何事だ!!!」っていう医師もいるそうですけど、そこは各々の信念があっていいと思います。
私の病棟管理のモットーは「石橋でも叩きまくる」です。確かに稀な合併症ではありますが
- 発症した際に速攻でICU行きになる
- ほぼ絶食状態のような状態が悪い心不全患者(多分LOS)
でuDKA8症リスクが高い
SGLT2iの早期導入で利尿剤の量を減らせることは様々な研究で言われていますが、個人的に気になるのが「初日でのSGLT2iの導入と数日後のSGLT2iの導入でoutcomeに差が出るのか」ってところです。そこで明確な差が出せない限りは、初期導入のメリットと万が一DKAになった時のデメリットとを比較して、、、、やっぱりデメリットを上回らない気がするんですよね〜〜。
なので私は初日から使う薬剤ではないと判断しています。まぁここはいろんな意見あってもいいと思うので自分で考えてみてください(丸投げ)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人的にはご飯がしっかり食べれており、LOSにもならないことを数日確認してから開始したい薬物です。なので比較的後回し、、、、とすると早期に安全に導入できるのってMRAしか残らないんですよね。
RA系阻害は利尿剤ではなく血管拡張薬なので、血圧が高めの心不全症例ではいい適応です。なので初手RA系阻害薬でも悪くないと思います。
が、急性心不全加療ではほぼ確実にループ利尿剤が入り、尿からカリウム排泄が亢進します。そこで低カリウム予防にMRAが効くんですよね。個人的にRA系阻害よりKの値が保たれるイメージです。
なので個人的にはMRAをfirstの治療薬にしています。AKIや高カリウムの副作用も、適宜採血でフォローしていけばとんでもないことにはならないはずです。
2番目の内服は血圧高め(で腎機能やKも大きな動きがなければ)でRA系阻害薬、体うっ血がまだ残っていてかつ食事摂取や排尿状況に大きな問題がなければSGLT2iって感じで組み立てています。
んで退院が見えてきたな〜〜っていうぐらいうっ血症状が取れて、ようやくβ遮断薬を導入します。
ちなみに、個人的には(特殊な事情がない限り)2剤同時に薬物の開始はしません。有害事象が出現した際にどちらが原因かわからなくなるので。肝障害や薬剤熱とかね。
無症状のHFrEFが来た時
非循環器内科医は対応しないんじゃないですかね笑。基本紹介症例のはずですし。後日書きますのでしばしお待ちを。
プロモーション
心不全の救急外来から入院までの流れをまとめました。ぜひ一度覗いてみてください。